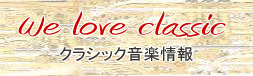|
これはまじめな話題です。
吹奏楽ではオリジナルの作品が比較的少ないため、コンクールなどで演奏される曲には、編曲作品が目白押しです。これは多くの人が貪欲にレパートリー開発に努力したおかげでもあります。
音楽著作物の著作権というのは、作曲家が書いた作品が演奏された場合に、入場料やレンタル楽譜の使用料として、作曲家に対価が支払われるというものですが、編曲の場合も同じように、出版されていない楽譜で、それを編曲する場合には、版権管理者に許可を得なければなりません。
この編曲について、吹奏楽コンクールで、過去に「ラヴェル事件」というのがあったそうです。ラヴェルの「ダフニスとクロエ第2組曲」を、出版社に無断で吹奏楽に編曲、演奏したため、版権管理者であるフランスのデュラン社から「許可しない」という通達があり、全国大会に出場できなくなってしまった団体があったのです。この事件をきっかけに、著作権への意識が一気に高まり、現在では、許諾申請も一般化するようになったそうです。
吹奏楽でも人気のある作曲家のラヴェルやR.シュトラウス、バルトークなどの版権は既に切れていますので編曲などは自由にできますが、中でも人気の高いストラヴィンスキーなどは、遺族の意向で一切の編曲は禁止されていて、版権が切れるのを虎視眈々と準備をしている吹奏楽マニアがいるそうです。
ちなみに、ショスタコーヴィチのように版権が切れていないにもかかわらず、編曲の申請さえすれば、どの作品も編曲、演奏可能という作曲家もいます。
音楽著作物の版権は、世界的に作曲者の死後50年は保護されています。(一部、「戦時加算」といって10年加えなければならない場合もある)、その版権が切れる前には、編曲についても版権管理者に許諾を得なければなりません。
現在、音楽著作権はJASRACが一括管理していますが、編曲の分野は管理外になっているそうです。版権がきれていない作品の「編曲」については、作曲家の遺族や版権管理者の許諾が必要になりますので、必ず確認してからにしましょう。JASRACに問い合わせをすれば、管理楽曲であれば、正当な権利者がわかるそうです。努力が無駄にならないように・・・。
|